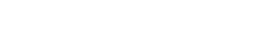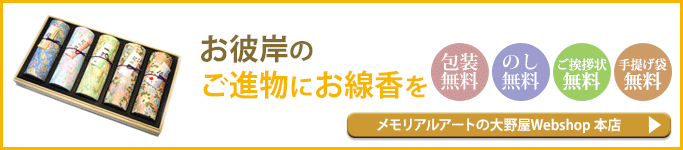お彼岸とは・・・
「彼岸」はサンスクリット語の「波羅密多」から来たものといわれ、煩悩と迷いの世界である【此岸(しがん)】にある者が、「六波羅蜜」(ろくはらみつ)の修行をする事で「悟りの世界」すなわち【「彼岸」(ひがん)】の境地へ到達することが出来るというものです。
太陽が真東から上がって、真西に沈み昼と夜の長さが同じになる春分の日と秋分の日を挟んだ前後3日の計7日間を「彼岸」と呼び、この期間に仏様の供養をする事で極楽浄土へ行くことが出来ると考えられていたのです。

お彼岸の期間
春彼岸 : 毎年3月の春分の日をはさんで前後3日合計7日間
秋彼岸 : 毎年9月の秋分の日をはさんで前後3日合計7日間
*** 2025年 春のお彼岸の日程 ***
彼岸入り:3月17日
お中日 :3月20日(春分の日)
彼岸明け:3月23日
*** 2025年 秋のお彼岸の日程 ***
彼岸入り:9月20日
お中日 :9月23日(秋分の日)
彼岸明け:9月26日
それぞれの初日を「彼岸の入り」、終日を「彼岸のあけ」といい、
春分の日・秋分の日を「お中日」といいます。

お彼岸の迎え方・準備
お彼岸でお参り出来ない、他家に伺う場合
●お墓参りするときは事前にお寺様または、霊園の管理事務所等に卒塔婆をお願いしておきます。
(宗派によっては不用のところもあります)
彼岸会
「お寺で故人の供養をすると同時に「六波羅密」の教えを会得する大事な行事です。 他の仏教国にはあまり見られない行事ですが、古来の民俗信仰とも深く結びついた「盂蘭盆会」や「施餓鬼会」と共に仏教の年中行事の中でも最も一般的に盛んに行われています。
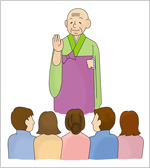
お墓参り
お墓参りは、ご家族みんなで出かけましょう。お墓は家族全員でお守りしていくべきものです。両親がご先祖様を祀る姿は後の世代に受け継がれてゆくことでしょう。
【持ち物】
※お墓参りに行くときには予め用意しておきましょう。
●お線香
●ろうそく
●マッチ (ライター)
●お花 (昔は"しきみ"が主に使用されていましたが、最近では四季折々のお花をお供えする方が多いようです)
●お供物 (お菓子や果物、故人の好きだったもの等)
【お掃除】
お墓参りに行ったらまず、お墓の清掃をしましょう。雑草が生えていたり、ゴミが散らばっていたりしては仏様に申し訳がありません。
●墓石は水をかけて洗い流します。
●水鉢や花立、香立てはゴミがつまりやすので丁寧に洗います。
●墓石の彫刻部分は、歯ブラシで細かい汚れを落とします。
●洗い流したら、タオル等で水気を拭きとります。
【お供え】
●お菓子や果物は直接置かず、二つ折りした半紙の上に置きます。
●水鉢にきれいな水を入れます。
●花立てに供花の長さを整え、お供えします。